2025年12月をもって、健康保険証とマイナ保険証の併用期間が終了します。政府の方針により、医療機関での本人確認はマイナ保険証が基本となる予定です。「まだ紙の保険証でも受診できるのでは」と思う人も多いでしょう。しかし、併用期間の終了後は医療費が高くなる可能性や手続きの負担が発生することも。この記事では、マイナ保険証の必要性や今後の制度変更の影響をわかりやすく説明します。
健康保険証とマイナ保険証の併用期間とは
健康保険証とマイナ保険証の併用期間とは、両方の保険証を使える猶予期間を指します。政府は当初、2024年末に紙の健康保険証を廃止する予定でしたが、医療機関や薬局の機器対応の遅れを考慮して2025年12月まで延長しました。
この期間中は、どちらの保険証でも医療機関を受診できます。ただし、2026年1月以降はマイナ保険証が原則となり、紙の保険証を使いたい場合は「資格確認書」を申請しなければなりません。この資格確認書は有効期限が1年で、毎年更新が必要となります。
表にまとめると次の通りです。
| 項目 | 健康保険証 | マイナ保険証 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 利用可能期間 | 2025年12月まで | 2026年以降も継続 | 併用期間終了後はマイナが原則 |
| 更新手続き | 不要(自動更新) | 不要(カード更新時のみ) | 紙の保険証は廃止予定 |
| 管理方法 | 紛失リスクあり | デジタル管理 | 紛失時の再発行も迅速 |
このように、併用期間中は選択が可能ですが、制度全体はマイナ保険証へ完全移行する方向で進んでいます。
マイナ保険証を持たないと医療費が高くなる?
紙の保険証を使い続けると医療費が高くなる、という話は一部事実です。2024年以降は、紙の保険証を使用する場合に発行される「資格確認書」で受診した際、初診時などで最大6円の加算が行われます。
| 区分 | 使用できる証 | 医療費負担 | 備考 |
|---|---|---|---|
| マイナ保険証 | マイナンバーカード | 通常通り | 医療情報が自動連携される |
| 紙の保険証 | 健康保険証(併用期間中) | 通常 | 2025年12月で終了予定 |
| 資格確認書 | 紙の代替証明 | 一部加算(最大6円) | 毎年更新が必要 |
この加算は罰則ではなく、システム運用や事務コストに対する補填の意味を持ちます。つまり、紙のままでも受診可能ですが、利便性とコストの両面で非効率となっていくのが実情です。
マイナ保険証に切り替えるメリット
マイナ保険証は、ただのカードではなく医療のデジタル基盤を支える仕組みです。主なメリットは以下の通りです。
| メリット項目 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 医療情報の一元管理 | 検査履歴・投薬履歴を共有 | 重複検査・薬の飲み合わせを防止 |
| 医療費控除の簡略化 | 医療費情報が自動反映 | 確定申告がスムーズになる |
| 紛失リスク低減 | 再発行がオンラインで可能 | セキュリティ強化 |
| 医療の質向上 | 情報共有による迅速診療 | 医療ミスの防止に寄与 |
また、マイナ保険証は利用者の利便性を中心に設計されており、医療の効率化やコスト削減にもつながると期待されています。
マイナ保険証に切り替えない場合のデメリット
一方、切り替えを行わない場合、次のような不便が生じます。
- 資格確認書を毎年更新する必要がある
- オンライン診療や電子処方箋サービスを利用できない場合がある
- 医療機関での受付処理に時間がかかる
| デメリット | 影響 | 補足 |
|---|---|---|
| 手続きの煩雑化 | 年1回の更新が必要 | 郵送や窓口申請に時間がかかる |
| 医療の非効率化 | 情報共有が限定的 | 医師間連携が遅れる場合あり |
| 費用負担の増加 | 初診時の加算発生 | 医療機関によっては対応費が異なる |
つまり、紙の保険証は「使えなくなる」のではなく「使いづらくなる」という段階に入っています。
高齢者や子どもへの対応
高齢者や子どもの場合、本人による手続きが難しいケースもあります。そのため、政府は代理申請制度を整備し、自治体でのサポート体制を充実させています。
| 対象者 | 手続き方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 高齢者 | 家族・自治体職員による代理申請 | 顔認証端末の設置が進行中 |
| 子ども | 保護者による申請 | 将来的に学校健診で活用予定 |
| 障がい者 | 支援員・施設職員による申請 | 医療連携支援体制の強化中 |
また、地域によっては出張登録会や自宅訪問サービスも実施されており、デジタルに不慣れな人も安心して切り替えられる環境が整いつつあります。
セキュリティと個人情報保護の仕組み
マイナ保険証のデータは、暗号化された通信を経由して送受信されます。情報へのアクセスには本人確認が必須で、無断閲覧は不可能な仕組みです。また、閲覧履歴が自動で記録され、利用者自身もマイナポータルから確認できます。
さらに、マイナンバーと医療データは物理的に分離されており、情報が一体化されることはありません。これにより、外部への漏えいリスクを最小限に抑えた設計となっています。
切り替えは早めに済ませるのが安心
マイナ保険証への申請は、スマートフォンやコンビニ端末から簡単に行えます。申請後、約2週間で交付されるのが一般的です。
| 手続き方法 | 所要時間 | 注意点 |
|---|---|---|
| スマートフォン申請 | 約10分 | 顔写真データが必要 |
| コンビニ端末申請 | 約15分 | マイナンバーカードを持参 |
| 郵送申請 | 約2〜3週間 | 書類不備に注意 |
早めに申請しておけば、医療機関での受付がスムーズになり、今後の制度変更にも柔軟に対応できます。紙の保険証を維持するよりも、利便性・コスト・安全性の面で優位です。
まとめ
マイナ保険証は、医療費を高くする制度ではなく、医療の質と利便性を高める改革です。
- 2025年12月まで健康保険証との併用が可能
- 2026年からはマイナ保険証が基本へ移行
- 紙の保険証利用では一部加算あり
- 情報管理・安全性は強化済み
現在は制度移行期であり、利用者に不便を感じさせないよう国全体で改善が進められています。マイナ保険証は「便利さ」と「安心」を両立させた新しい医療の形です。
早めに切り替えを済ませておくことで、手続きの手間を減らし、将来的な医療費負担の不安を避けることができます。今こそ、安心して利用できる医療環境への一歩を踏み出す時期です。



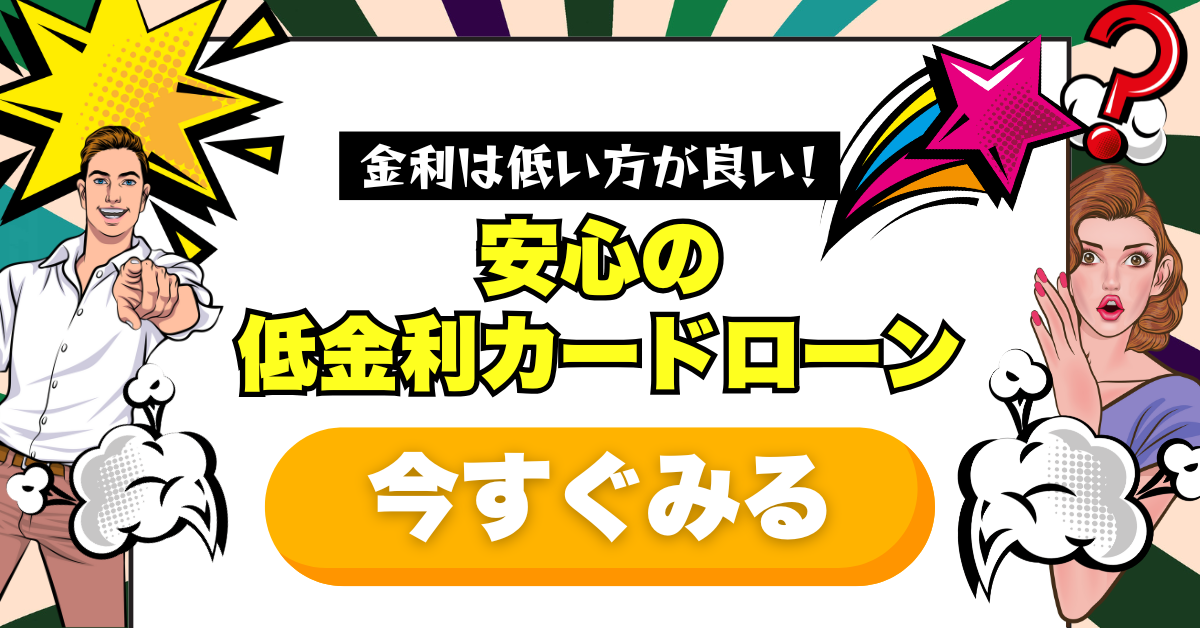




コメント